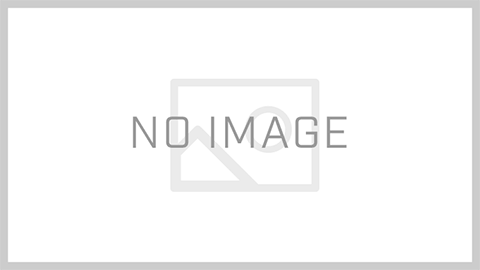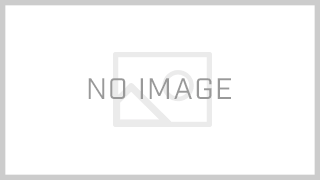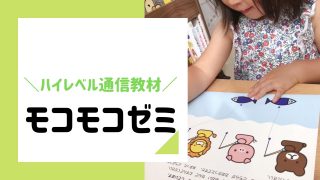指先が器用になる「紐通し遊び」。
市販品の紐通しおもちゃを探すと、色んな種類があって悩みますよね。
月齢や成長発達に合わせて、子どものおもちゃを選ぶって難しい…。
そこで、紐通しおもちゃを手作りと100均で代用する方法をご紹介します。
子どもの成長発達や得手不得手好みに合わせて色々試せる手作りと100均で、紐通しおもちゃを作って遊びましょう!
紐通しのねらい・育脳効果
紐通しのねらい・育脳効果は、「指先の巧緻性」です。
紐通しは、左右の手で穴のあるものと紐の別々のものを持ち穴に紐を通す、という左右の手がそれぞれ違う動きをして協力しなければ出来ないのです。
非常に繊細で複雑な指先の動きを求められる紐通しは、子供には難しいです。
しかし、大人がやる様子を見せて本人がいくつかできるようになるときっと夢中になる遊びですよ。
紐通しおもちゃの種類は2つある
紐通しおもちゃは大きく分けて2種類あります。
ビーズ通しタイプ

ビーズ通しタイプは写真のような、紐にビーズを通すタイプのおもちゃです。
赤ちゃんの頃から始めるならば、もっとビーズの大きさも穴も紐も全て大きいものから始めます。
ボード通しタイプ

ボード通しタイプは、穴の空いたボードに紐を通すタイプ。
靴紐通しや、縫い差しに繋がっていく紐通しおもちゃです。
本記事では、ビーズタイプの紐通しおもちゃについてご紹介していきます。
専用のおもちゃは買わなくていい理由
私が紐通し専用のおもちゃを買わなくて良いと思う理由は3つあります。
成長発達と共にサイズを変えていくから
最初は、ビーズも紐も穴も大きなものからチャレンジしていきます。
最初は難しいと思いますが、出来たらもう簡単。
どんどんステップアップしていく必要が出てきます。
その度に買い替えとなると、コストもかかるし場所も取りますね。
家の中や100均に代用出来るものがたくさんある
この後詳しくご紹介しますが、家の中や100均には穴が空いているものいっぱいありませんか?
ラップの芯、ミシンのボビン、ストロー…。
大きさは様々ですが、むしろそれが紐通しおもちゃにはぴったりなのです!
買ったものに食いつかない可能性
これは我が家の経験ですが、幼児教室で使っていた紐通しおもちゃを自宅でもやろうと誘ってみたのですが全くしようともせず…。
これが紐通し専用のおもちゃだったら、丸っとひとつ無駄になってしまうなと思いました。
ただ、市販の紐通し専用のおもちゃは子どもが食いつく色やデザインなので成長発達に合ったものを選べば大丈夫かもしれません。
紐通しおもちゃの手作り・代用品5つ
我が家は、紐通し専用のおもちゃは一切無し。
家の中にあったものや、100均で代用しています。
大きさ、難易度順にご紹介していきます。
トイレットペーパーの芯

トイレットペーパーの芯を輪切りにして折り紙を貼ったリングです。
我が家では0歳後半の頃から始めたので、これくらい大きくないと難しいようでした。
色のはっきりした折り紙を貼ると、より食いつきが良いと思います。
プラステン

プラステンのリングを紐通しのリングに代用する方法。
幼児教室ではこれを紐通しのスタートにするところがいくつかありました。
プラステンは、紐通し以外にもペグさしや見立て遊びなど0歳から小学生くらいまで使える「木のおもちゃの王様」と呼ばれる名品。
しかし、我が家の場合(0歳後半〜1歳頃)は全く出来ず!
チャレンジするけど出来なくて、ぶん投げてました…。
周りの子は小さめの紐通しに移っていく中で、我が家は家でトイレットペーパーの芯で練習してたなぁ…(遠い目)
▼1歳くらいでこれくらいのサイズの紐通し出来るってすごい…。
トイレットペーパーの芯を経て、我が家もプラステンの紐通しが出来るようになりました!
ウッドビーズ

フライングタイガーコペンハーゲンという北欧雑貨を扱うお店で購入したウッドビーズ。
サイズ的には、HABAのものより少し小さめサイズになります。
同じような難易度だと、ミシンのボビンもだいたい同じ大きさだと思います。
ビックストロー

ビックストローはタピオカ用のストローで、通常よりも太めのストローです。
100均で購入したものです。
ビックストローは、ウッドビーズよりもビーズ自体は小さいけれど、穴は大きいのが特徴。
うちの子どもは、小さいものをつまむのは得意だけど、小さい穴に紐を通すのが苦手だったのでウッドビーズよりもこちらが出来たのが先でした。
ずっと紐通し嫌いできましたが、ビックストローにしたあたりから出来上がりの作品がアクセサリーっぽくなりよくチャレンジしてくれるようになりました。
100均のビーズ

2歳半の今は、100均(ダイソー)の大き目のビーズにチャレンジしています。
こんなに可愛いのに100円!
紐はタコ糸を使っています。

リボンやキャンディが可愛くて、好きな色を選んでネックレスにしてウフフと遊んでいます。
見ていて、今が1番紐通しが好きそうな感じがします。
うちは女の子なので、やっぱり可愛いものでやりたかったのかなぁなんて思っています。
子どもが難しそうにしていたら「紐」を工夫しよう
子どもが紐通しが難しそうにしているようなら「紐」に一工夫を加えましょう。
子どもが紐通ししやすい紐の特徴は「固めで芯があること」。
紐の先端を上に向けてもピンと立っているようなナイロンの紐(新聞を縛るようなもの)や、書類を綴る先端が固い紐(写真の左から2番目)が良いと思います。
もしくは、紐の先端をテープで巻いてあげる。

0〜1歳は手芸用モール(写真の右、黄色と赤色)くらい針金でピンとした物が良いと思います。
我が家はこれに気付くのが遅く、0〜1歳台はあまり紐通しで遊ばなかったなぁと思います。
それも難しそうなら、棒通しがおすすめです。
0歳〜1歳前半なら、ビーズタイプにいきなり行くより棒通しから入ると楽しくできると思います。
可愛らしくて、持ち運びも出来て、窒息の心配も少ないですね。
ベビーカーに乗っている子がこれを夢中でやっていたのが、とても可愛かったです。
手作り紐通しおもちゃの注意点
手作り紐通しおもちゃを乳幼児に与える上での注意点は、窒息と誤飲。
東京消防庁によると乳幼児は39mm(トイレットペーパーの芯の大きさ)を通る大きさのものなら、口に入れてしまい飲み込んでしまう危険があるとのこと。
これよりも小さいものを紐通しおもちゃとして乳幼児に与える時は「知育教材」として大人が見守れる時にだけにしましょう!
詳しくは▼
乳幼児の窒息・誤飲について【東京消防庁】
本記事で挙げた紐通しおもちゃの中では、プラステン以降は全て誤飲と窒息のリスクのある大きさになります。
十分注意して、紐通しおもちゃで遊ぶようにしましょう。